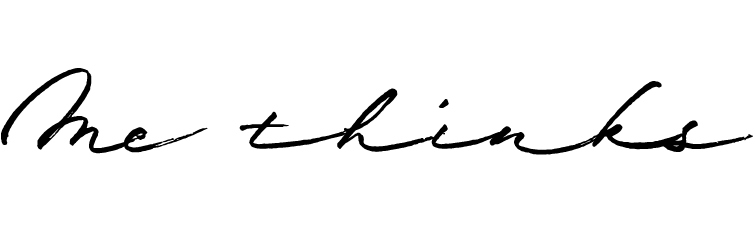これは昨日の深夜に半分絶望しながら書いていた文章なんだけど、今日読み返してみてもけっこうひどめの迷走具合だったので記録として遺しておく。こういう、公開していないうだうだした文章がひたすら下書きとかメモとかに溜まっている。まあそれもいいよね。
わたしは何者か。何がわたしをわたしにするか。もういちど自分が何者なのか、何がしたいのかを確認しなきゃいけない時期が来ている気がする。
去年の今頃はバイクの免許をとっていた。いつ死ぬかわからないなら後悔しないように、という思い切りで。納車時は体が小さくてバイク屋さんに心配されたけど今いちおう乗れていて、コロナウイルス禍で実家に帰らなければならない時に電車を使わず帰れるようになった。
年が明けてから始まった、声を出す練習は、大きな声やナレーション的なイントネーションが最初恥ずかしいというか、無意識の抵抗が大きかったけど、練習していたら納得いく声の出し方で録音ができるようになってきた。
型通りの、ルールが細かく決められた台本をいくつも書いた。新しいデザインをいくつも作って納品した。いくつも作っていると、質は上がるし、精神的にも楽にできるようになる。無意識の脳みその筋肉というか、わたしの中にあるマッチョな意識が、仕事をまわしてくれる。
練習は裏切らない。できないことをある程度できるようにするのは、結構かんたんで、短期間の集中と、軽めの努力というか習慣化、意識化するだけで、たいていのことはこなせるようになる。
なんども会議をしなければいけないプログラムに、いくつか参加した。最終的に、深く思考しなければならない場面で息切れした。
新しく長編戯曲を書こうとしても、頭が働かずに苦しんだ挙句布団に潜ってしまう。
人間関係のトラブルで、SNSでひどいメッセージをもらったり、傷付いたり恐怖することが何度かあった。いまだって結構怖がりながら生きている。
電話でなんども怒られた。書いたことを通して、思想までも全否定された。私にとって大事な部分をありえない、と言われた。
深い思考力を伴わないスキルを上げるのはかんたんだ。頭を使わなくても、身体が覚えてくれる。言語よりも感覚を使う方が、じつは楽で、自動的だし、A4のチラシのレイアウトが今更地獄のように崩れたり、簡単なことで入稿に失敗したりはしない。
文章はちがう。いくら時間をかけても、怒られるようなものを書いてしまうことがある。否定され、しかもその否定が胸の奥まで刺さる。
逆撫でするような文章を書く人もいる。きっとなんの意識もしてなくて、私が一方的に被害妄想を抱いているだけなのだが、日々ほどほどな絶望と一緒に暮らしていると、まあそれくらいは簡単に、嫌な部分を感じとったりする。
そこで。思考をしない形で人生を進めるのはどうかと提案をしてみる。「考える人」なんて読んでいた私よ、残念だね、もう状況は変わった。君を苦しめる人との関係を、どうやっていけばいいかを考える必要は無くなったのだよ。もし君が不安を感じる相手がそれ以上近づいたら、警察にでも連絡すればいいだろう。君がそれで満足するならば。解決、とはそういうことだ。今度は君が君に向きあうばんだ。でも、それをすることすらもう辛いなら、諦めたっていいんだよ。夢とも言えない何かを。それがなくなったとしても、生きていける程度の仕事はくるし、大抵まわる。貯金はきっと増えるし、なんの心配もいらない。君の感覚が死ぬまでは、少なくとも。
深く、なにかを考える途中に、かなり硬めの岩盤が埋まっているようだ。跳ね返される。お前は、お前を守るだけで、精一杯なんだろ。いや違うと言いたい。壊してしまいたい。でも、その岩をむりやりに砕いてしまったら、心も粉々になってしまうんじゃないかなんて想像する。あんなに柔らかかった頭が、がちがちになっている。今まで傷付いたり恐れているものを思い出しては、脳が警告を出して、全てをストップさせようとしている。
私は何者なんだろう。どうしてこんな人生を歩んできたんだろう。どうしてうまくやれなかったんだろう。誰も傷つけずに、自分も傷つかずに済む方法、なんて、いや、まて。ないな。ない。無理。無駄。
諦めない、ならば。その岩盤にじっくり向き合い、心は壊さないように、ゆっくり砕く、あるいは、温めて溶かしたり、少しずつ食べていく、必要がある。君はなんて固さなんだ~とかいいながら、ゆっくりやっていくしかない。その間、いくらやきもきしても進めないが、あわてないぞ。癒えるまで。こちとら生きるために演劇を選んだんだ。そうやすやすと手放すものか。
っていうことを書いていたら、高校生の時に考えていた物語を思い出した。急に。
星の郵便屋と名乗る謎の男が、死んだ父からの手紙を届けに晃士郎の家のベランダに降り立つ。父からの手紙はある星の超新星爆発の力を借りて空から流れ星のように降ってきて、郵便屋がそれを拾い集めて届けに来る。まあ、それはウソなのだが、謎の男はなんども晃士郎の元を訪ね、晃士郎は彼の母、心を壊してしまった母のことなどを話す。
母と息子はしばらく会えていない。彼が中学に上がるころから離れ離れになった。母は心を壊し、彼を育てきれなかったことへの罪悪感から、母の心はさらに深いところに浸かってしまった。
高校二年生の冬。晃士郎は勉強だけが得意で、人との関わりはとても苦手だった。国立の大学に無理せず入れる学力があるため、父の遺産でやりくりできるだろう。料理は上手くない。ただ、下宿先の大家さんがスパイスに凝っていて週に一度カレーを届けてくれる。遠くに住んでいる父方の祖母からは沢山の野菜が届くし、父の古い友人が時折訪ねてきたりもする。明るくていい人だったとみんなが言うので、そうだったんだろう。自分とは正反対だ、などと思う。
夜中まで本を読んだり、勉強をしている彼の元に郵便屋は突然やってきて、とりとめもない話をして帰っていく。そして、ときどきたずねる。夢はないのか、と。晃士郎は夢を持たない。点数だけが信じられる。預金通帳だけが信じられる。将来は銀行か、願わくばあまり人と関わらずに済み、心が乱れない職に就きたいと思っている。
郵便屋がこなかった日、晃士郎は夢をみる。父は科学館の職員で、よくプラネタリウムに招待してくれたこと、一緒に天体観測をしたこと。どうして忘れていたのだろう。父は8年と半年前に亡くなった。小学校二年生の夏だった。
郵便屋が届けるのはいつも空白の手紙だ。なにも書かれてないじゃないかと文句を言っても、いつも笑ってかわされる。
「流れ星だからね」と。
望遠鏡を覗く。
8.6光年離れたシリウスがかがやく。
「シリウスはああやって輝いているけど、実はひとつの星じゃないんだよ。AとBのふたつの連星なんだ。大きな輝きの隣に、小さいけど確かに輝く恒星がみえるだろ。」
「おれはあの小さいほうだな、小さい光。Aは、父さんみたいなひとをいうんだろうな」
オリジナルで書いていた小説はここから先どう進むのかわからないけど、頭の中に彼らの存在はずっと残っているから大事に大事に作っていたんだろう。戯曲にしてみるのもいいかもしれない。