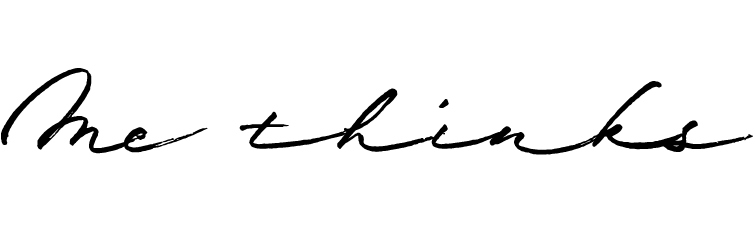「こんなに長く生きられたので私たちは満足です」という親たちの穏やかな顔や言葉を忘れられない。小学一年生のとき初めてその子の家に遊びに行った。子供にとっては夢のような世界、私には与えられなかった、たくさんのポケモンのぬいぐるみ、ゲームソフト、たまごっち。私はそういうおもちゃが欲しくてもあまり買ってもらえない子どもだった。ただ、おもちゃがなくても私たちは水の公園に集まった。水の公園でみつけたアメンボ、笹の葉っぱを船にして流すこと、そのほか特に理由はないけれど水が流れるのをただただ見つめていたこと、そこで遊んだメンバーはめずらしく男の子も混ざっていた。私の家の近所に住む「一緒に通ったらどう?」と勧められた子たちとは違う友だち。多分紅茶とケーキが(いつでも家に友達のためのケーキが置いてある家庭のことをあまり信用していない、私はひねくれているから)出てきたりしない、元気で気楽で楽しい子どもたち。中学に上がってからはほとんど話さなくなってしまったけど。あの公園の近くに住んでいた友だちの家。行き方は覚えてるけど、怖くて近づけない。近づく理由もない。こんなに長く生きられたので私たちは満足です、そうですか、あなた方が満足でも私は満足していなかった。彼女が描いたお花畑とそこに住んでるお姫様の絵は何年経っても覚えている。あの絵が完成しないまま、学期が終わって私たちは卒業した。美術の先生は漫画みたいなタッチの絵に対して批判的で、私がちょっとした賞を取ったCGの絵も絶対に認めてはくれなかったし、同じく彼女が描こうとしている絵に対してもそうだった。そしてその先生が褒め、私もとても信用している、群を抜いてすばらしい才能を持った友達もいた。それでも、彼女に「**の描く絵みたいに描きたい」と言われて調子に乗った中学生の私は、どの口が言えるかわからないようなアドバイスをしながら一緒に絵を描いた。淡い水彩の色を少しずつ少しずつ慎重に重ねた。もしかしたら、たった二、三時間や、もっと少ない時間だったと思うけど、でも私たちはその時、幼馴染みとして一つの絵を同じ美意識で一緒に完成させようと思っていた。完成はしなかったし、もう会えなかった。なかなかこない彼女の絵を先生がひっぱり出して何か言っていた。これどうしようかしら。その絵は、ちゃんと家に持って帰られたのだろうか。捨てられてしまったんだろうか。いろいろなきっかけがあるけど、自分にはこのことがとても大きなきっかけになっている。誰かが死んだそのあと、何かを期待することはできない。そのあとすぐ、お別れがくるなんて思っていなかったし、その後の私は初めて受ける大人からの怖くてわからなくて思い出すだけで心臓がバクバクするような問題を処理することで頭がいっぱいになっていた。そんなはずはないのに、つらいことしか思い出せない。つらいことのなかでこのことだけが美しい思い出みたいに書いているけど、だって美しいんだもん。こんなに美しかったのはこれくらいしかない。そういう消化の仕方をすることでしか彼女のことを思い出せなくなっているけど、多分ここには本当のことしかないと思う。本当に15歳の私たちはちゃんと作ろうとしていたしきっとちゃんと生きようとしていた。