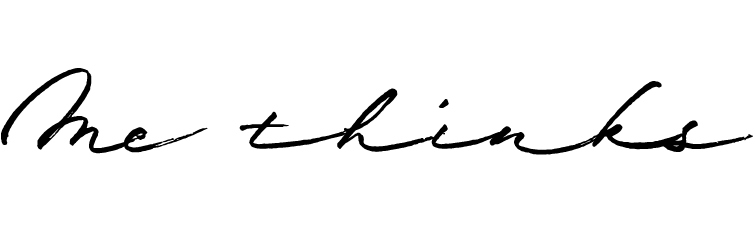『海辺のカフカ』で、田村カフカくん(仮名)が「牛乳をあたためて飲む」ことをよくしていて、なんとなく好感を持てる。最近はそのまねをして、朝起きた時や夜寝る前、落ち着かない時に飲むようにしている。お湯を沸かしてコーヒーや紅茶を淹れるという行為が大変、という気持ちになっているときにも重宝している。それにうちの電子レンジにはなんと「牛乳」というボタンがある。すごくないか、牛乳だけのために用意されたボタン。吹きこぼれないようにしてくれているのだと思う。ありがたい。
このように物語の中に出てくる食べ物が自分の生活を作っているのかもしれないと「ハウルの動く城」のカットをみて思う。私はよくベーコンエッグや野菜を焼いたものを一緒に作ってヨーロッパの朝ごはんダ!みたいな気持ちで食べたり、バターでスクランブルエッグをいかに上手く作れるか挑戦したり、イタリア人の真似でコーヒーにビスケットだけで朝ごはんダ!みたいな行動をしているのだがこれは実家でそうだったというわけではなく、完全に一人暮らしをしながら、完全に一人で習得した料理習慣のひとつだ。自分で作ったご飯はいつでも、どんなに適当でも、なぜかとてもおいしいと思う。しかし、おいしい、のために作っているわけじゃないような気もする。
子が母に料理を習う、という風習はまだ世には残っているのだろうか。少し憧れるけれど、私はそのフェーズを知らずに家を出てしまった。子どもの頃、母の調子が悪かった時、週に一、二度はボンカレーを食べる可能性、を感じながら暮らしていた。まあなんでもいいよと思っていた(本当に)。チキンラーメンを作るのが好きな(食べるより作るのほうがやっぱり面白い)子どもだったので、いかに上手に卵を上に載せて作るかにいつもうきうきしていた。しかし、全部食べられないことも多かった。
十代の頃の自分の食欲は今思えばとても「病的」なほど少なかったように思う。食べられなかった。小さなお弁当も残さざるを得ない、という食べられなさ。母の料理でこれが好き、というのは、今ならいくつか思えるが、当時はまったくわかっていなかった。大学生になって自分の昼ごはんは毎日冷凍の「茄子入りミートソース」だった。それだけは本当に毎日食べていた。とにかく、何も考えずに生命維持できる物ならなんでも良いと思っていて、その中でも茄子と肉の入ったスパゲッティは毎日食べても飽きなかった。量も少なかったし。
母親のつくるご飯が美味しいと思い始めたのは一人暮らしを始めた後だった。それは単純な「実家の味」への有り難みだけではなく、かなりの割合で、母の調子がよく食事を作るハードルが少し下がったことからきているように見えた。料理は「気」をつかうものだと思う。鬱で物が選べず何をつくればいいかわからないときに作る食事よりも、今日はこれを作ろう、と決められる日の方が美味しいものが作れるんだなと気づいた(これは創作にもまっすぐに関係する。料理は創作だものね)。だから、そんな風に少し昔より調子のいい母の料理を食べると本当にけっこうなんでもおいしくて、今まで伝えそびれていた「おいしい」を、なんの違和感もなく伝えられるようになったことに気づいたとき、ちょっと泣いた。
人間に欲は必要だと思った。欲のままにできるということが自由であり、心の健康の一助だよね。欲をあまりに持たなすぎたり、そんなのダメ、なバリアが強い時ほど、人は幸せな顔をしていない。ちょっとくらい良いよねと笑う人のほうが、なさけなくだらしなくもあるが安心できたりする。